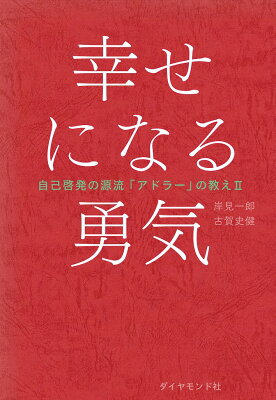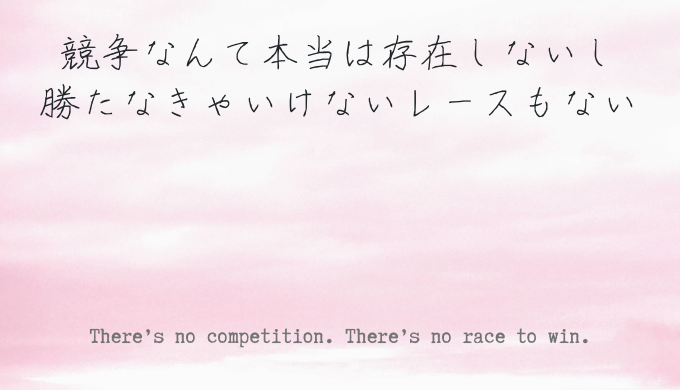
「嫌われる勇気」を最初に読んだときは、難しいなと感じました。
大ベストセラーである理由も、わかりませんでした。
本当にこれを実践できている人がいるのだろうか、と。

続編の「幸せになる勇気」を読んで、その違和感が少しほぐれました。
次のようなことが書いてあったからです。
もしもアドラーの思想に触れ、即座に感激し、「生きることが楽になった」と言っている人がいれば、その人はアドラーを大きく誤解しています。アドラーがわれわれに要求することの内実を理解すれば、その厳しさに身を震わせることになるはずですから。
やはり、アドラー心理学は難しいのです。
なぜ、難しいか?
ひとことで言うと、「愛される生き方」から「愛する生き方」への転換を説いているからだと思います。
そして、「ほめられること」は求めないという、「承認欲求の否定」。
それは実は、「普通でいること」の勇気だったのです。

私たちは、常にその逆をやってしまうので、なかなか幸せになれないのだそうです。
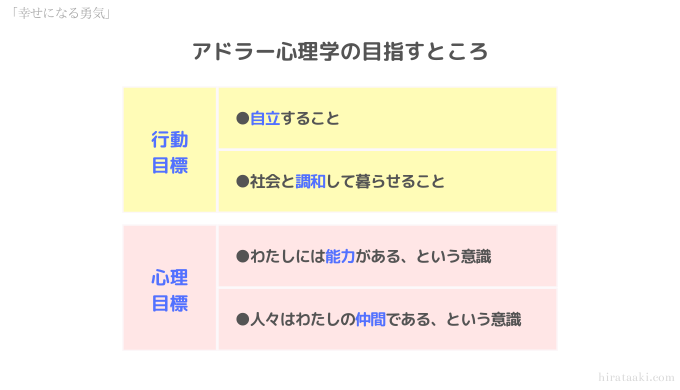
最重要:「普通であることの勇気」を持つ
自分は「世界の一部である」ことを認める
われわれは頑迷なる自己中心性から抜け出し、「世界の中心」であることをやめなければならない。「わたし」から脱却しなければならない。甘やかされた子ども時代のライフスタイルから、脱却しなければならないのです。
(by 幸せになる勇気)
「自分が世界の中心」という意識を捨てる
具体的には……
- 「その他大勢である」ことを受け入れる
- 「特別なわたし」を、あきらめる

「その他大勢」だなんて、イヤだよ。
「その他大勢でいたくない」「特別な存在でいたい」という努力は、「ありのまま」とは正反対だといいます。
「ありのまま」生きる
「普通であることの勇気」が足りていないのでしょう。ありのままでいいのです。「特別」な存在にならずとも、優れていなくても、あなたの居場所はそこにあります。
(by 幸せになる勇気)
- ありのままでいい
- 普通でいい
- 特別じゃなくていい
- 優れていなくていい
それでも、自分の居場所はある
それが、大人の生き方であり、「自立」。

「ありのまま」の本当の意味とは
平凡なる自分を、「その他大勢」としての自分を受け入れましょう。
(by 幸せになる勇気)
「ありのまま」とは、実はすごく普通で、平凡なこと。
つまり。
「ありのままに生きたい」と、ことさらに主張する人は……
本当は「ありのまま」を求めていない。
「特別で優れた自分になりたい」という願望を持っている。
では、なぜ、「特別で優れていたい」という願いを持つようになったのでしょうか。
私たちは、なぜ不幸なのか
これはちょっと、衝撃的な事実。
私たちは、口では「幸せになりたい」と言いつつも。
実は。
「不幸になる行動」を、積極的に選んでいる場合が多いのだといいます。
不幸になるための行動 = 問題行動には5段階あります。
必ず、1から順番に歩んでいきます。
問題行動の5段階
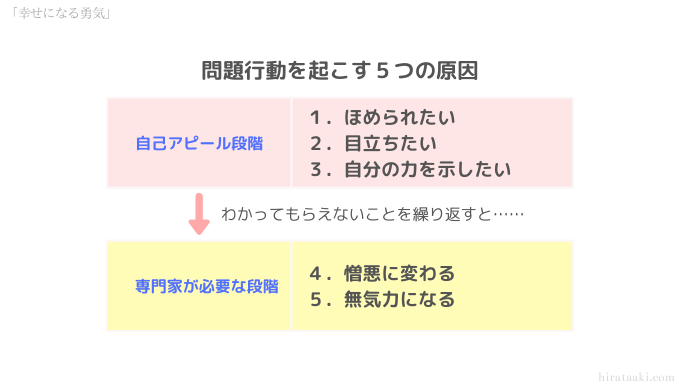
- 称賛の要求
- [すべての問題の入り口]
- 目的:ほめてもらうこと
- 行動:「いい子」を演じる
- 注目喚起
- [ほめられないから、注目を集めようとする]
- 目的:目立つこと
- 行動:悪いことをする、「できない子」として振る舞う
- 権力争い
- [注目を得られないから、争いに入る]
- 目的:自分の力を誇示すること
- 行動:反抗する、無視する
- 復讐
- [争うことをあきらめ、相手が嫌がることを繰り返す]
- 目的:愛してくれなかった人への復讐
- 行動:ストーカー、自傷行為、引きこもり
- 無能の証明
- [これ以上の絶望を味わいたくなくて、課題から逃げる]
- 目的:見捨ててもらうこと
- 行動:無気力になり、愚か者を演じる
1~3までは自己アピール段階。
4番の復讐の段階からは、専門家への相談が必要なレベル。
5段階のすべてに貫かれているのが、承認欲求
「こんな私を、誰か承認して」という思い。
もっと言うと、「特別なわたしでいたい」という願い。
最初は、「ほめられたい」気持ちからスタートし、どんどんエスカレートしていく。
だからアドラーは、問題行動をやめる手段として、「承認欲求」を否定するのです。
「自己承認」に切り替えないと、重度の病気になるから
「専門家が必要なレベル」になる前に、軌道修正したいですよね。
そのためには。
他者からの承認に依存するのではなく、自己承認に切り替えること。

私たちはなぜ、他者に「ほめられたい」と思うのでしょうか。
根源的な欲求は、「所属感」
アドラー心理学では、人間の抱えるもっとも根源的な欲求は、「所属感」だと考えます。つまり、孤立したくない。「ここにいてもいいんだ」と実感したい。
(中略)
では、どうすれば所属感を得られるのか?
……共同体のなかで、特別な地位を得ることです。「その他大勢」にならないことです。
(by 幸せになる勇気)
所属感とは、「居場所がほしい」という欲求
- 人間の根源的な欲求は、「所属感」
- 孤立したくない
- 「ここにいてもいい」と思いたい
- 居場所がほしい
- 居場所を作るには、どうする?
- その他大勢にならずに、
- 特別な地位を得る
- 特別になるためには、どうする?
- ほめられたい
- 注目を集めたい
- 権力を持ちたい
「その他大勢」にならないために。
「特別なわたし」でいるために。
ほめられたいし、注目を集めたいし、権力を持ちたい
その根底には、一貫した思いが。
- もっと私を尊重してほしい
- もっと私を愛してほしい
そのためなら何でもするんですよね。
注意すべきは、「いい子」でいることや、社会的な成功を目指すことさえも。
「特別な地位を得たい」という問題行動である可能性があること。
「いい子」でいないと、愛されないと思っているからから。
仕事を頑張ることでしか、自分は愛されないと思っているから。

「愛されたい」というのは、「甘えた子どもの生き方」であるといいます。
子どもの目的は、「世界の中心」に立つこと
常に、大人を支配しようとしてきた
子どもたちは、自活することができない。泣くこと、つまり己(おのれ)の弱さをアピールすることによって周囲の大人を支配し、自分の望みどおりに動いてもらわないと、明日の命さえ危うい。彼らは甘えやわがままで泣いているのではない。
(by 幸せになる勇気)
子どもは、「どうすれば、親に見捨てられないか」を、かなり利己的に学習しているといいます。
- 泣きわめけば、親は自分の望みを叶えてくれるし
- 愛されれば、親は自分を見捨てないだろうと思う
だから。
「どうすれば、もっと愛されるか?」を試行錯誤する。
そうして、「愛されるためのライフスタイル」を形成する。
性格とは違い、自分で選びとっているもの。
私たちは、「どんな自分なら愛されるか」を基準にライフスタイルを選択した
両親の性格・性向を見極め、兄弟がいればその位置関係を測り、それぞれの性格を考慮し、どんな「わたし」であれば愛されるのかを考えた上で、自らのライフスタイルを選択します。
(by 幸せになる勇気)
- 自ら置かれた環境を考える
- 両親の性格を見きわめる
- 兄弟の位置関係を検討する
- 家族全員の性格を考える
じっくりと観察を重ねたうえでの選択。
なんと。
私たちの行動パターンは、「性格の問題」ではなかったんです。
「これなら愛されるだろう」と、利己的に選んだもの。
「愛されること」「自分が世界の中心に立つこと」が、生きる戦略
「愛されるためのライフスタイル」とは、いかにすれば他者からの注目を集め、いかにすれば「世界の中心」に立てるかを模索する、どこまでも自己中心的なライフスタイルなのです。
(by 幸せになる勇気)

子どもは、それでいい。
そうしないと生きていけないから。
でも、大人になったら、ライフスタイルを再び選択し直さなければならないですね。
「こうすれば愛される」という子どもの判断には、間違いが多いから。
そのためには、「愛される」のではなく、「愛する」を選択することです。
「愛する」への転換
大人は、「自分は世界の一部だ」と了解しなければならない
すべての人間は、過剰なほどの「自己中心性」から出発する。そうでなくては生きていけない。しかしながら、いつまでも「世界の中心」に君臨することはできない。世界と和解し、自分は世界の一部なのだと了解しなければならない。
(by 幸せになる勇気)

それは、「愛される」ではなく、「愛する」への転換。
自分から誰かを愛する
与えられる愛の支配から抜け出すには、自らの愛を持つ以外にありません。愛すること。愛されるのを待つのではなく、運命を待つのでもなく、自らの意思で誰かを愛すること。それしかないのです。
(by 幸せになる勇気)
- 愛を与えられるのを待つ
- 「愛されたい」「ほめられたい」
- 自分が世界の中心
「自分が世界の中心」をやめるためには、「愛される」のではなく、「愛する」こと。
「愛しかない」というのが、「幸せになる勇気」の結論です。

そこが、アドラー心理学の実践の難しさですね。
「愛すること」は、厳しく、困難で、勇気が試される
アドラーの語る「愛」ほど厳しく、困難で、勇気を試される課題はありません。その一方で、アドラーを理解するための階段は、「愛」に踏み出すことで得られます。いや、そこにしかないといっても過言ではないでしょう。
(by 幸せになる勇気)
「愛すること」は、厳しく、困難で、勇気が必要。
傷つきたくないからです。
しかし、「愛されること」だけを求めるのも、とても苦しく、困難な道。
本当の幸せを感じることができないからですね。
だからこそ。
嫌われることも覚悟しつつ、「愛すること」に踏み出す。
それが、「幸せになる勇気」の核心です。

まとめ
共同体のなかでどのように生きるべきなのか。他者とどのように関わればいいのか。どうすればその共同体に自分の居場所を見出すことができるのか。「わたし」を知り、「あなた」を知ること。人間の本性を知り、人間としての在(あ)り方を理解すること。
(by 幸せになる勇気)
- すべての悩みは、対人関係の悩みである
- すべての喜びもまた、対人関係の喜びである
つまり私たちは、人間関係の中でしか幸せになれないのだというのです。
具体的には、人間関係の中で、「自分の居場所を見つけること」。
問題は、どのように振る舞えば「居場所が見つかるか」を、私たちは教わったことがないという事実。
だから子どもは、「自己中心的」にしか判断できません。
大人になって、なんか違うと思っても、「じゃあ、どうしたらいいの?」ということが、わからない。
結局は、「特別なわたし」をあきらめられないまま、ずっと同じことを繰り返してしまいます。
多くの大人たちもまた、自分の弱さや不幸、傷、不遇なる環境、そしてトラウマを「武器」として、他者をコントロールしようと目論(もくろ)みます。心配させ、言動を束縛し、支配しようとするのです。
そんな大人たちをアドラーは「甘やかされた子ども」と断じ、そのライフスタイル(世界観)を厳しく批判しました。
(by 幸せになる勇気)
幸せになれない人は、不幸であることで特別になろうとしているのです。
それがアドラーの言う、トラウマも傷も、すべては言い訳にすぎないという意味です。

トラウマを否定し、承認欲求を否定し、「甘えた子ども」を脱却する勇気。
「普通でいる勇気」をもつかどうか。

どうしても「愛される」を求めてしまいます。
「嫌われる勇気」と「幸せになる勇気」は、そんな自分の願望を知るためのヒントがたくさん書いてあるので、詳しく知りたければオススメですよ。
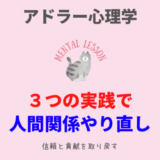 アドラー心理学【信頼と貢献】人間関係が築けないのは、味方だと思えてないから
アドラー心理学【信頼と貢献】人間関係が築けないのは、味方だと思えてないから
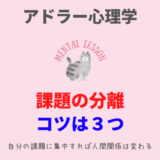 アドラー心理学【課題の分離3つのコツで】人間関係は激変する
アドラー心理学【課題の分離3つのコツで】人間関係は激変する
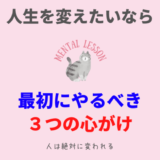 アドラー心理学【あなたは絶対に変われる】過去は関係ない
アドラー心理学【あなたは絶対に変われる】過去は関係ない
 劣等感の強い人が何度も考えたいこと【自分の長所に】目を向けるために
劣等感の強い人が何度も考えたいこと【自分の長所に】目を向けるために
 【過去との和解】エンプティ・チェアとインナーマリッジのすすめ
【過去との和解】エンプティ・チェアとインナーマリッジのすすめ
 自己肯定は成長の邪魔になる|失敗したときに思い出すといいこと
自己肯定は成長の邪魔になる|失敗したときに思い出すといいこと