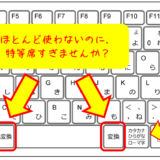1.【生きる意味】人生最後の日、あなたは何を思いたいですか?~人の気持ちがわかるということ
2.「文字の力」で過去を消せる?~人間が、サーカス小屋のゾウになれない理由
3.お風呂の排水溝が詰まった!高圧洗浄で流した結果、そこに詰まっていたものとは?~長年の苦しみを一気に流した瞬間
4.人が変わる極意は、圧倒的な「量」と「時間」!~「励まし」という大雪を降らせよう
5.【文章の目的】なぜ、言葉にして伝えることは難しいのか?~こわれかけの空気清浄機の話
6.事件は「今」起きてるんじゃない。「過去」に起きてるんだ!~人間の二大欲求を満たせ!
7.え? 私は毒親に育てられたの?~自分のせいにすると自分を好きになれない理由
2020年5月7日追記
上の2番目の記事(生きる意味)を天狼院書店さんに記載していただいてから、ちょうど一年が過ぎて。
思いがけず、天狼院書店さんより、次のようなご連絡をいただきました。
この度、ライティングゼミ編集部にて、昨年の全記事の中でも特に優れていた作品を編集部「セレクト中のセレクト」として選出しておりまして、
その中で平田様の『【生きる意味】人生最後の日、あなたは何を思いたいですか?~人の気持ちがわかるということ』の作品が出てまいりました。
今回、5月からはじまる「ナレーション講座」にて、こちらの記事を、朗読の題材として練習に使用させていただきたく、ご連絡させていただきました。
朗読で、記事の良さがより伝わるよう、ナレーション講座のゼミ生が練習をしていく内容となり、HPにアップされているものをそのまま読ませていただければと思っております。
人に強く伝わるものがある、力のある作品かと存じますので、ぜひ、今回、朗読の練習の題材として使用させていただければ幸いでございます。
仕事ではないので、お金が発生するわけではありません。
でも、誰かに喜んでいただけるなら、書いた甲斐があったと思います。
自分の経験を書くことには、思いがけない喜びがあるものですね。