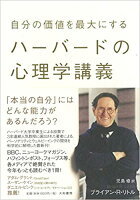青年は幼いころから自分に自信が持てず、出自や学歴、さらには容姿についても強い劣等感を持っていた。そのおかげだろう、過剰なほど他者の視線を気にしてしまうところがあった。そして他者の幸福を心から祝福することができず、いつも自己嫌悪に陥っていた。
by 嫌われる勇気
これは、「嫌われる勇気」に出てくる話。

まったく同じだ。
劣等感を強く持ってしまった場合、私たちはどうしたらいいのでしょうか。
この記事で学ぶこと
劣等感の強い人が、まず考えたいこと
1.「私は、わたしのために生きる」と決める
あなたは、あなただけの人生を生きています。誰のために生きているのかといえば、無論あなたのためです。そしてもし、自分のために生きていないのだとすれば、いったい誰があなたの人生を生きてくれるのでしょうか。われわれは、究極的には「わたし」のことを考えて生きている。そう考えてはいけない理由はありません。
by 嫌われる勇気
「劣等感」とは、他人との比較から生じるもの。
つまり。
他人を考えて生きている。
だから、まずやるべきことは。
「私は、わたしのために生きる」と決めること。
自分を中心に考えていいんです。

でも、そうすると「自分勝手だ」と怒られるし。
2.「誰かの期待を満たすためには生きない」と決める
たとえば仕事の主眼が「他者の期待を満たすこと」になってしまったら、その仕事は相当に苦しいものになるでしょう。なぜなら、いつも他者の視線を気にして、他者からの評価に怯え、自分が「わたし」であることを抑えているわけですから。
by 嫌われる勇気
「あなたは自分勝手だ」というセリフの裏には何があるのか。
それは。
「あなたは、なぜ私の期待に応えてくれないの?」
要するに。
「自分勝手だ」と言っている人も、自分勝手だと言えますね。
ならば、その人に応えるべき理由も、ないのです。

それでもやっぱり、「できないこと」が劣等感なんだけど。
劣等感を持つことも、悪いことではありません。
「健全な」劣等感であるならば。
3.「健全な劣等感」を持つ
劣等感も、使い方さえ間違えなければ、努力や成長の促進剤となるのです。
by 嫌われる勇気
- 「できないこと」を、「できるようになりたい」と追求すること
- 「理想の自分」になること
成長の方向へといけるのであれば、健全な劣等感です。
こういう気持ちは、自分を成長へと導いてくれるので、悪くありませんね。
つまり。
他人との比較ではなく、「できない自分」と、「できるようになった自分」との比較をする。

「健全な劣等感」ということは、「不健全な劣等感」があるってこと?
「不健全な劣等感」を捨てる
- 健全な劣等感
- 「理想の自分 ⇔ 今の自分」との比較
- 不健全な劣等感
- 「他人 ⇔ 自分」との比較
- 不幸自慢(=言い訳)
- 「Aだから、Bできないんだ」
- 他人との比較・競争
- 他人に勝ちたい
つまり。
- 「言い訳の世界」から抜け出す
- 他人との「勝ち負け」にこだわらない
1.「言い訳の世界」から抜け出す
「わたしは学歴が低いから、成功できない」と考える。あるいは「わたしは器量が悪いから、結婚できない」と考える。このように日常生活のなかで「Aであるから、Bできない」という論理を振りかざすのは、もはや劣等感の範疇に収まりません。
by 嫌われる勇気
- 容姿が悪いから、恋愛がうまくいかない
- 両親が離婚したから、自分はこうなった
- いじめられた経験があるから、人を信じられない
「Aだから、Bできない」と言う人は、「Aさえなければ、Bできる」と思っている。
けれども、「Aが消える」ことは、ありませんよね。
ということは。
そもそも「自分は、Bをしない」と決めているのです。
- Aだから、Bできない
- Aさえなければ、Bできるはず
- でも、Aはなくならない
- だから、自分はBをしない
- どうせ無理
- こんな自分だから
これが「言い訳」であり、要するに「不幸自慢」。
「どうせ自分はこうなんだ。だって、◯◯だから」と。
不幸自慢におちいったら、次のようなセリフに変換してみましょう。
「ちょっとだけBにもトライしてみようかな」
「AだからBできない」とは、本当は「Bがしたい」という気持ちだからです。

でも、やっぱり「したくない」のかもしれない。
やりたくないことに気づいたときは、単純に、「自分は、Bはしない」と決めてみましょう。

重要なのは、「不幸自慢をする自分に勝つ」ことであって、「他人との勝ち負け」ではありません。
2.「他人との勝ち負け」にこだわらない
他者の幸福を「わたしの負け」であるかのようにとらえているから、祝福できないのです。
by 嫌われる勇気
負けた気がする
劣等感や空虚感を招く一番の要因は、何といってもこの気持ち。
「うらやましい」と思うのも、「あの人だけズルい」と思うのも。
常に、他人との比較・競争で「負けたくない」と思っているからです。
われわれが歩くのは、誰かと競争するためではない。いまの自分よりも前に進もうとすることにこそ、価値があるのです。
by 嫌われる勇気
- 無意識にまかせると、どうしても他人と比較してしまう
- だから「意識的に」、毎日、思い出す
- 目的は、今の自分よりも前に進むこと

だけど、やっぱり比較しちゃう。
他人との比較から抜け出すために
1.誰も、本当の姿を見ていないことを知る
美女は人からすれば美しいが、魚がそれを見れば水底にもぐり、鳥がそれを見れば空高く飛び去り、鹿がそれを見れば駆け足で逃げ出す。
いったい四者のだれが本当の美を知っているのだろう。
by 莊子
絶世の美女だとしても、「誰が」見るかによって行動が変わります。
- 人が見れば
- 美しくて、近づく
- 魚が見れば
- 怖くて、水底にもぐる
- 鳥が見れば
- 怖くて、飛び去る
- 鹿が見れば
- 怖くて、走り去る
誰も、「その人の本当の姿を知らない」というのが莊子の結論。
それぞれの性格や考え方があるので、当然、見方が違います。
- 美人すぎて「怖い」と思う人
- 美人すぎて「ずるい」と思う人
- 美人だから「うらやましい」と思う人
- 美人だから「素敵だ」と思う人
たとえ褒められても、けなされても。
それは、ひとつの見方にすぎないんですよね。
2.「劣等感は主観である」と知る
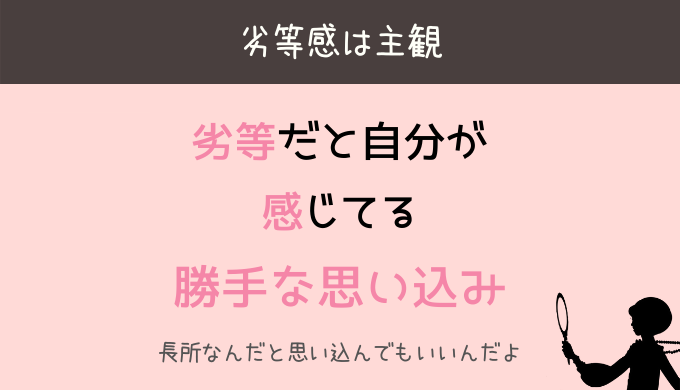
たとえば「身長の低さ」に劣等感を抱いている場合
もしも比べるべき他者が存在しなければ、わたしは自分の身長が低いなどと思いもしなかったはずです
by 嫌われる勇気
「自分は身長が低い」とは、「自分よりも高い誰か」と比べて、相対的に感じていること。
「相対的に」とは、「絶対ではない」という意味です。
「主観」は自分で選べる
自分の身長について長所と見るのか、それとも短所と見るのか。いずれも主観に委ねられているからこそ、わたしはどちらを選ぶこともできます。
by 嫌われる勇気
自分の性質を、長所と思うか。短所と思うか。
主観ならば、自分で選べる。
たとえ、他人から何かを言われたとしても、その意見を採用しなければいいだけなんです。

でも、他人の意見を聞くことって、大事なんじゃないの?
3.「柔軟な視点」を持つ
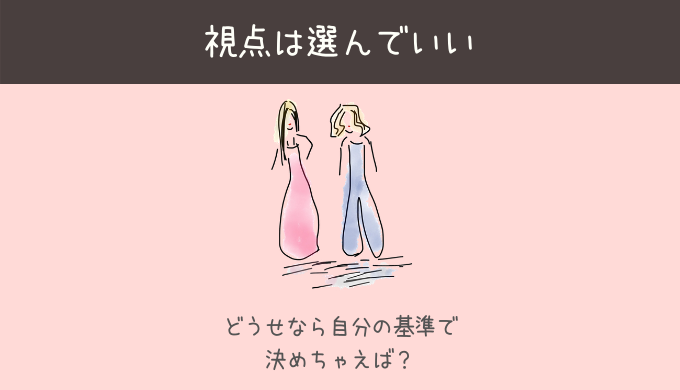
わたしたちが特定の視点から世界を見ていること自体は問題ではない。
問題なのは、自分の視点が普遍的だと思い込み、心を閉ざしてしまうことだ。わたしたちは厳密な区別をもうけ、あまりに確固とした分類や価値観をつくってしまう。
by ハーバードの人生が変わる東洋哲学
人によっても、動物によっても、いろんな視点がある。
だから、どんな視点を持っても自由です。
ということは。
どの視点も、「絶対に正しい」ものはない。
ならば、押し付けるものでも、押し付けられるものでも、ありませんよね。
「視点は選んでいい」のです。
そして、ひとつに固定しない「柔軟性」も大事。
一つの評価基準で、自分や他者をとらえるべきではない
「ハーバードの心理学講義」では、「枠にハメない」ほうが自由になると言われています。
「視点は、固定しない」。
柔軟に変えていくもの。
「一つの評価基準」だけで、決めないことですね。
まとめ
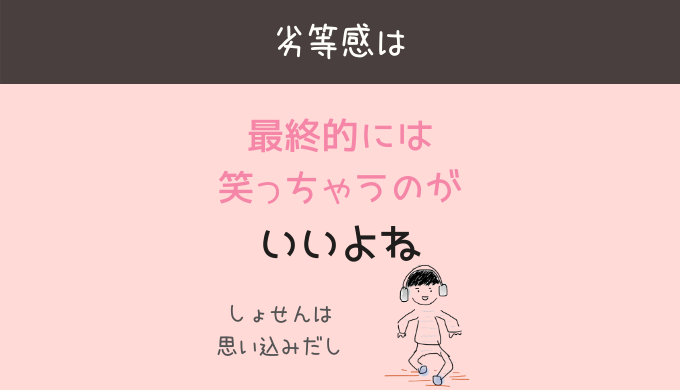
【何度も考えたいこと】
- 「私は、わたしのために生きる」と決める
- わたしのことを考えて生きてていい
- 「誰かの期待を満たすためには生きない」と決める
- 他人からの評価におびえない
- 「健全な劣等感」を持つ
- 「理想の自分」⇔「今の自分」を比較
- 「過去の自分」⇔「今の自分」を比較
- できるように努力する
【不健全な劣等感を捨てるために】
- 「言い訳の世界」から抜け出す
- 「できるようになる」努力をする
- 積極的に「やらない」と決める
- 「他人との勝ち負け」にこだわらない
- 「負けた気がする」をやめる
- 誰かとの競争ではない
【他人との比較から抜け出すために】
- 誰も、本当の姿を見ていないことを知る
- 人によって視点が違う
- 「劣等感は主観である」と知る
- 相対的な比較は、絶対ではない
- 「柔軟な視点」を持つ
- ひとつに固定しない

劣等感は、使い方次第。
よいほうに活用することもできます。
一番のポイントは、やはり「他人と比べない・勝とうとしない」ことですね。