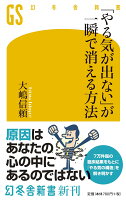何かやりたいと思ってるけど、本当に気力がない
やる気が出ない原因とは、実は。
「自分は何でもできる」という万能感

いや、「何もできない」から、無気力なんだけど
自分は無力で、自分でコントロールはできないのだという地点に立ち返ることが、最初の大事なポイントです。
「やる気が出ない」が一瞬で消える方法
- やる気が出ない原因は、「万能感」を持ってるから
- やる気を出すには、「無力感」が大事

逆じゃないの?
人を無気力にさせる原因は、「万能感」
万能感とは
- 「自分は何でもできる」
- すべては自分の思いどおりになる
- だから、自分で何とかしなきゃ
- 「自分は何でも知っている」
- 何が正しいのか、知っている
- どうすればうまくいくか、知っている
- だから、すべて自分でジャッジしなきゃ
- 「間違い探し」「犯人探し」が得意
- 「正しいかどうか」「善か悪か」が好き
- 「好きかどうか」は苦手
- 自分は、何でもできるスーパーヒーロー
- 自分は、何でも知っている正義の味方
- 自分こそが神である
- 万能感 = 自分は何でも知っているスーパーヒーロー

スーパーヒーローにあこがれるけど
すべてが許せなくなる
万能感が働いていると、どんどん自分が偉い人間・仕事ができる人間であるように感じ、たとえば目上の人や偉い相手に対しても、「〇〇さんは自分の思い通りに動いてくれない」とか「私が望むように優しくしてくれない」という感情が湧きやすくなります。そうして相手の気に入らないところがどんどん目につき、増えていくのです。
「やる気が出ない」が一瞬で消える方法
- すべてが正しくないと、許せない
- すべてが思いどおりにならないと、許せない
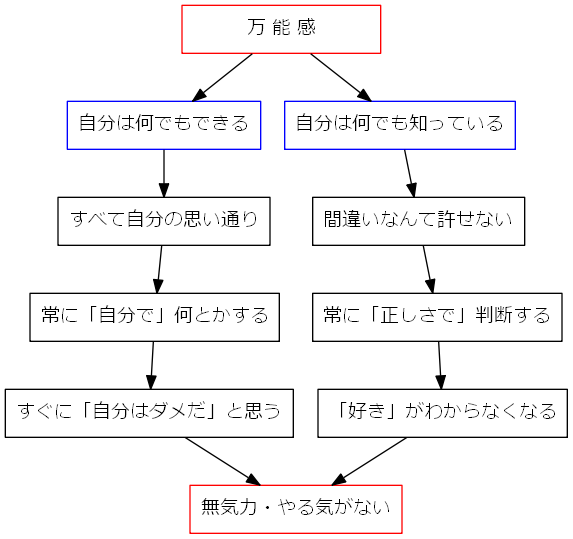
「気に入らないこと」だらけで不安が強くなる
自分のせいにしたり、自分で判断したりするという感覚が、万能感です。
「やる気が出ない」が一瞬で消える方法
- 自分のせいかもしれない
- 自分が、間違っているかもしれない
- 自分は、何もできていない
- 思いどおりに、うまくいくはず
- 努力した分、見返りがないとオカシイ
- 理想と現実のギャップに落ち込む
- ○○しなければ
- 前向きにならなければ
- ポジティブにならなければ
- 常に戦っていなければ
- 自分で判断しなければ
- 今の言い方、間違ってたかな?
- この選択、間違いかな?
- 私の何が悪かったのだろう?
- いったい、誰が悪いんだろう?
- なぜ、私(スーパーヒーロー)の言うことを聞けないの?
- なぜ、こんなこともできないの?
- 相手は、私の話を聞かない、頑固な人だ
- 相手は、正しいことができない、ダメな人だ
- すべてを知っているかのように振る舞う
- 知らないなんて、ありえない
- 自分は偉い、自分は正しい
結果:夢も気力も、もてなくなる
- 正しさばかりを追い求める
- 謙虚さ・感謝を忘れる
- 正解か不正解かだけの、とても味けない世界
- 思いどおりにならないイラだち

万能感って怖い。どうしたらいいんだ?
やる気を取り戻す5つの対策
対策1:とにかく休む
闘争と安心のホルモンバランスが崩れているから
- 闘争ホルモンの「ノルアドレナリン」
- 戦っていたい
- 安心ホルモンの「セロトニン」
- 休んでいたい
ホルモンを抑えるには、待つしかない
「闘争 V.S. 安心」の闘いが終わらないと、ホルモンの量がアンバランスになる。
ホルモンを抑えるためには、待つしかない
だから、待つしかないそうです。
対策2:「善悪」「正誤」を手放す
「前向きに動かなければいけない」とか「〇〇でなければいけない」と考えるのは万能感によるジャッジです。
「やる気が出ない」が一瞬で消える方法
- 正しいのは、どっちだろう
- 自分の何が悪いんだろう
- どうすれば「善い」んだろう
- あいつは間違っている
- 万能感は、「犯人探し」が好き

正しいかどうかの判断をしないなら、何を基準に選べばいいの
対策3:「快・不快」で決める
「快・不快」のリズムを大切に
不快と感じたものは避けていいですし、快ばかりを感じようとしていいのです。おいしいと感じるものを食べ、まずいものは避けていい、ということです。
「やる気が出ない」が一瞬で消える方法
快・不快・快・不快・快・不快
快か不快かだけ。
- 「快感」を求めちゃいけない
- 人生、楽しいことだけじゃない
- 「好き」だけで選んだら怒られそう
- 「快」を選んでみよう

「快」がわからない
対策4:「万能感を捨てる」と決める
- 「自分のせいだ」という思い
- 「正しさ」
- 「うまくいくはず」という期待感
- 「何もできていない」という焦り
- 「理想と現実のギャップ」に苦しむこと
- 「常に戦い続けなきゃいけない」というプレッシャー
- そもそも人間は万能ではない
万能感を捨てると、謙虚さが手に入る
- 自分は、無力である
- 自分は、責められる存在ではない
- 自分は、何もコントロールできない
- 一人では何もできない、力のない自分。だから人と助け合う。
- 「自分が生かされている」と思う
- 「自分のために世界がある」と感謝する

やっぱり万能感が出てきちゃう
対策5:万能感に気づいたら、何もしない
- 「何もできない」ことを受け入れると、「何でもできるようになる」
- 「何とかしなきゃ」は万能感だから
まとめ
万能感で生きると、こうなる
- 本当は「快」なのに、
- 無理して、嫌いなフリをする
- 本当は「不快」なのに、
- 我慢して、頑張り続けてしまう
- 常にジャッジしている
- 何が「いいか・悪いか」
- 誰が「正しいか・間違っているか」
- ◯◯したほうがいい
- ◯◯しなきゃ
- ◯◯しておかないと困るだろうな
- 自分のせい
- 正しさ
- 「うまくいくはず」という期待感
- 「何もできていない」という焦り
- 「理想と現実のギャップ」に苦しむこと
- 「常に戦い続けなきゃいけない」というプレッシャー
- 「何とかしなきゃ」は万能感
無力感で生きると、こうなる
- 「自分が生かされている」と思うから
- 「自分のために世界がある」と感謝の念がわくから
- 「何もしない」のが無力感 = 無力な自分を受け入れる
「何もしない」のが一番。
しょうがないなぁと、「無力な自分」を受け入れる。
判断を差し挟まずに、コツコツと我が身を経過観察し、ある日心にストンと落とし込まれた風景は、その人にとっての全データになっていきます。それはその人にしかわからないデータだからこそ、その風景によって「私」は何のために生きているのか、ということも見えてくるのです。
「やる気が出ない」が一瞬で消える方法

「万能感」と「無力感」の関係は、衝撃的だった
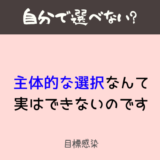 今の目標、本当に自分で選んだもの?【自分らしい選択】をするために
今の目標、本当に自分で選んだもの?【自分らしい選択】をするために
 ストレスを避けると【10年間でウツになる】本当に幸せな人の習慣とは
ストレスを避けると【10年間でウツになる】本当に幸せな人の習慣とは
 自分を責めるよりも【セルフ・コンパッション】憂鬱さを解消するたった一つの方法
自分を責めるよりも【セルフ・コンパッション】憂鬱さを解消するたった一つの方法
 自分の性格で悩まなくていい【性格テストに信ぴょう性なし】「◯◯な人」と決めたら不自由になる
自分の性格で悩まなくていい【性格テストに信ぴょう性なし】「◯◯な人」と決めたら不自由になる
 感情的になりやすい人が【今すぐやめたい】3つの考え方
感情的になりやすい人が【今すぐやめたい】3つの考え方
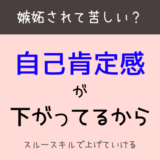 嫉妬や攻撃をされて苦しいのは【自己肯定感が低いから】スルースキルで強くなれる
嫉妬や攻撃をされて苦しいのは【自己肯定感が低いから】スルースキルで強くなれる