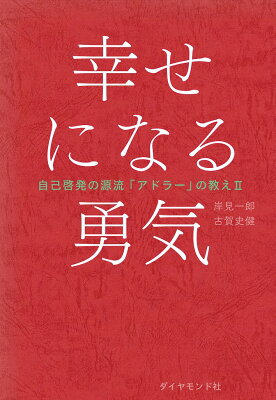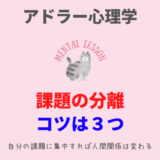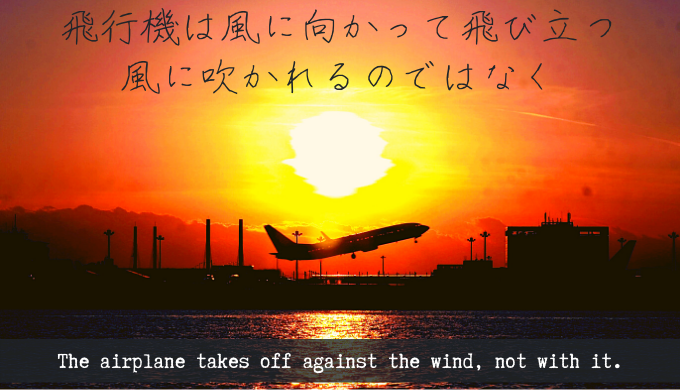
「嫌われる勇気」とは、人間関係を築いていく勇気。
そのためには、相手を信頼し、貢献することが必要です。

でも大丈夫。
自分を受け入れ、「課題の分離」ができるようになるだけで、グッとラクになります。
- 自己受容
- どんな自分も受け入れてあげる
- 課題の分離
- 解決可能か・不可能かを切り分ける
↑この2つができるようになると。
相手を敵ではなく、味方だと感じられるようになる。
味方だからこそ、自然と相手を信頼し、貢献できるようになる。
もしも、自己犠牲を感じるのであれば……
相手を「敵」だと思っているから。

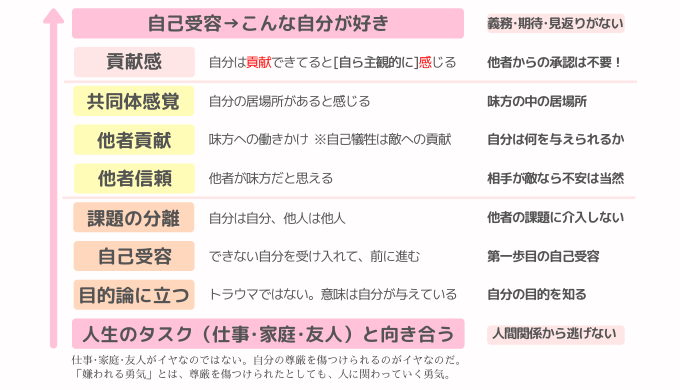

相手を信頼する3つの実践
なぜ相手を信頼できなくなるかといえば。
信頼するメリットがわからなくなってしまったからですよね。
なのでまずは、改めてメリットを思い出してみること。
特に、次の3つを意識するといいと思います。
- まずは「課題の分離」をする
- 「深い関係のほうが喜びがある」ことを思い出す
- 「無条件のほうがラクである」ことを思い出す
1.まずは「課題の分離」をする
裏切るのか裏切らないのかを決めるのは、あなたではありません。それは他者の課題です。 あなたはただ「わたしがどうするか」だけを考えればいいのです。
(by 嫌われる勇気)

だから、人と関わりたくない。
人間関係を避けるようになってしまう理由の第一は、これですね。
もう裏切られたくない
ツラい思いを、たくさんしてきたのですよね。
怖いしイヤになるのは、当たり前。
けれども。
「課題の分離」を知れば、恐怖心から抜け出せるようになります。
相手が裏切るかどうかは、「相手の課題」だから
自分の課題は、「相手を信じること」。
自分の中の、「信じる力」を受け入れるのです。
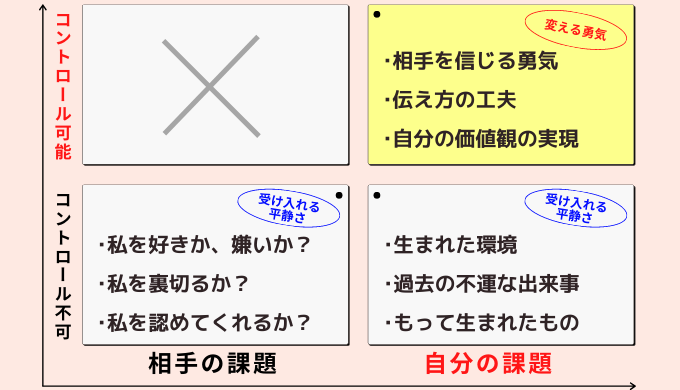
ありのままの自分を受け入れ、「自分にできること」と「自分にはできないこと」を見極めることさえできれば、裏切りが他者の課題であることも理解できるし、他者信頼に踏み込むこともむずかしくなくなるでしょう。
(by 嫌われる勇気)
「ありのままの自分を受け入れる」とは。
「どうにもならないこと」「自分には変えられないこと」を、受け入れること。
たとえば。
- 不遇な環境に生まれてしまった
- 生まれつき持っている性質
- 親の育て方が悪かった
- 上司が理不尽だった
- いつも、イジメられてばかりだった
- あの人は、私を嫌いに違いない
「変えられない過去」や、「どうにもできない自分の性質」「コントロールできない他人の気持ち」ってありますよね。
それに対して、「こんなの、イヤだ!」とか、「なぜ自分は……」と、抵抗するのをやめる。
それが、「受け入れ」です。


本当に、人間関係って必要なのかな?
2.「深い関係のほうが喜びがある」ことを思い出す
浅い関係であれば、破綻したときの痛みは小さい。しかしその関係から生まれる日々の喜びもまた、小さいはずです。「他者信頼」によってもっと深い関係に踏み込む勇気を持ちえてこそ、対人関係の喜びは増し、人生の喜びも増えていくのです。
(by 嫌われる勇気)
人間関係に飛び込めない理由は……
人間関係にメリットがあると思えなくなったから
傷つくだけで、いいことは何もない、と。
けれども。
人生に深い喜びをもたらしてくれるものは、他人との「深い関係」しかないと、アドラーは主張します。
- 浅い関係
- 痛みは浅い
- 喜びも浅い
- 深い関係
- 信頼が深い
- 喜びも深い
今、日々の生活がつまらなくて、喜びも感動もないのであれば。
深い関係を築けてないことが原因。
「傷ついたから喜びがない」のではなく。
「深い関係がないから喜びがない」
だから解決策は、「もういちど深い関係にチャレンジする」しか、ありません。

「無条件の信頼」です。
3.「無条件の関係のほうがラク」だと思い出す
「相手が裏切らないのなら、わたしも与えましょう」というのは、担保や条件に基づく信用の関係でしかありません。
(by 嫌われる勇気)
信頼と信用の違い
- 信頼=深い関係
- 「頼りになる」と信じること
- 客観的根拠は、なくていい
- 無条件でいい
- 信用=浅い関係
- 過去の実績や成果によって、取引すること
- 根拠付き:○○してくれたら、信じる
- 条件付き:担保があれば、信じる
↓これは、条件付きの信用
- 「相手が裏切らなければ」信じる
- 「私を好きになってくれるなら」貢献する
人間関係に「if」があるのが「浅い関係」
「take があるなら、give するよ」という関係ですね。
「無条件」とは、「if」のない関係

怖すぎる……
「根拠がいらない」ことには、メリットがある
信頼に根拠がいらない、ということは。
自分にも大きなメリットとして返ってくるんです。
それは……
「貢献できているかどうか」にも、根拠がいらないから
「信頼」が無条件なら、「貢献感」も無条件になるんですね。

承認欲求から解放されるんです。
- 課題を分離すれば、「相手の裏切り」が自分の課題ではないことを知ることができる
- 深い関係からは、深い喜びを得られる
- 無条件の信頼からは、無条件の貢献感が得られる
- 承認欲求が必要なくなる
他者を信頼すると、他者が「敵」ではなく「味方」になるし。
相手が「味方」だと思えると、貢献は自然にできるようになります。
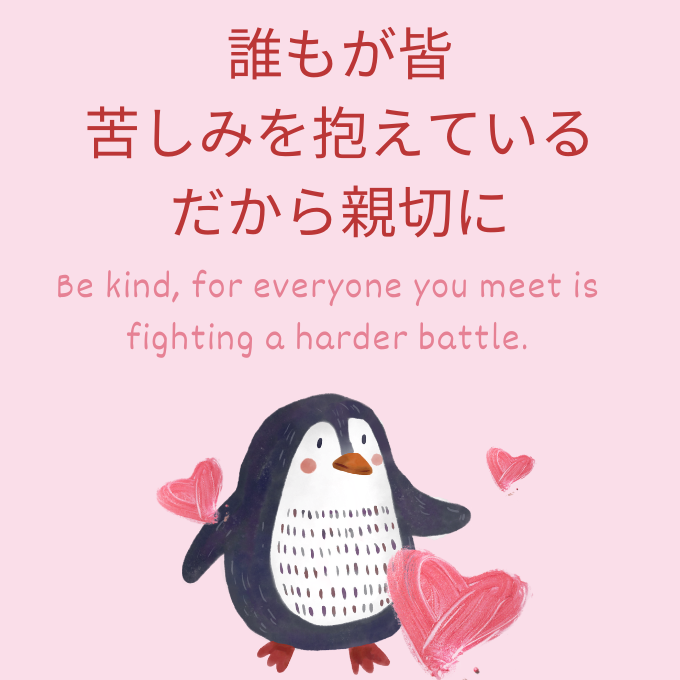
他者貢献のメリット
1.貢献する相手は、味方
仲間である他者に対して、なんらかの働きかけをしていくこと。貢献しようとすること。それが「他者貢献」です。
(by 嫌われる勇気)
「仲間である他者」とは、つまり、「味方」。
- 誰にやる?
- 「味方」にやる
- 何をやる?
- なんらかの働きかけ
他者貢献とは、「味方」に貢献すること。
ここが大事ですね。
誰でもいいわけじゃない。
- 他者貢献:味方に対するギブ
- 自己犠牲:敵に対するギブ

そもそもの関係性を見直してみたほうがいいのかな。
2.貢献する目的は、「自分の価値を実感する」こと
他者貢献とは、「わたし」を捨てて誰かに尽くすことではなく、むしろ「わたし」の価値を実感するためにこそ、なされるものなのです。
(by 嫌われる勇気)
- 誰にやる?
- 「味方」にやる
- 何をやる?
- なんらかの働きかけ
- 何のためにやる?
- 「わたし」の価値を実感するため
「わたし」を捨てる道ではない。
むしろ、「わたし」を生かす道。

3.貢献するメリットは、さらなる自己受容
他者に貢献するからこそ、「わたしは誰かの役に立っている」と実感し、ありのままの自分を受け入れることができる。
(by 嫌われる勇気)
- 誰にやる?
- 「味方」にやる
- 何をやる?
- なんらかの働きかけ
- 何のためにやる?
- 「わたし」の価値を実感するため
- 何が実感できる?
- 自分は役に立つ人間だ
- 自分は有益な人間だ
- メリットは何?
- 自分をさらに受け入れることができる
何もせずに、「自分を受け入れる」ことは、まだまだ自己満足の領域。
一方で。
他者に貢献することによる自己受容には、喜びがついてきます。
「役に立っている」と実感できるから。
自己受容→他者信頼→他者貢献→自己受容の、好循環。
この感覚がなければ、味方への貢献とはいえない。
喜びがともなっているかどうかが、目安。
最大の幸せは、自分を好きになること
「自分は役に立っている」という思い
人間にとって最大の不幸は、自分を好きになれないことです。この現実に対して、アドラーはきわめてシンプルな回答を用意しました。すなわち、「わたしは共同体にとって有益である」「わたしは誰かの役に立っている」という思いだけが、自らに価値があることを実感させてくれるのだ。
(by 嫌われる勇気)
人間にとって最大の不幸は、自分を好きになれないこと
ならば、逆に
人間にとって最大の幸福は、自分を好きになれること
……ですね。
- 誰にやる?
- 「味方」にやる
- 何をやる?
- なんらかの働きかけ
- 何のためにやる?
- 「わたし」の価値を実感するため
- 何が実感できる?
- 自分は役に立つ人間だ
- 自分は有益な人間だ
- メリットは何?
- 自分をさらに受け入れることができる
- そんな自分をどう思う?
- こんな自分が好き
人生のタスクと向き合う理由は、自分を好きになるため
- 自分は、共同体にとって有益であると感じること
- 自分は、誰かの役に立っていると感じること
他者に働きかけることなくして、自分を好きになることはできない。
だから、人生のタスク(=仕事・家庭・友人)と向き合わねばならないのです。
人間関係と向き合うことは、苦しいことではなく、自分を好きになること。

自分が嫌いってことは、深い人間関係がないからなのかな。
まとめ
人間関係に踏み込むためには、まずは自分を受け入れ、課題を分離すること。
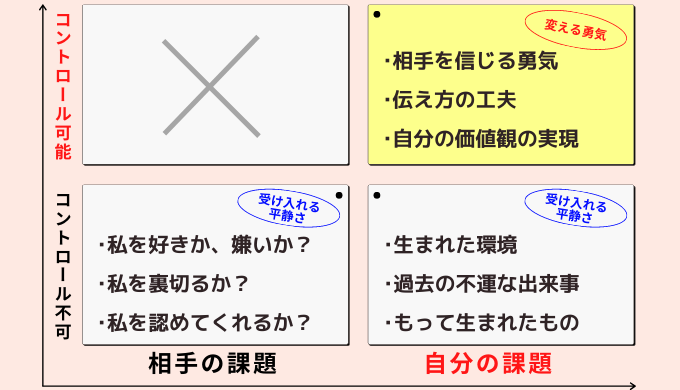
なぜなら。
他者の気持ち・態度・行動をコントロールすることは、自分には「できないこと」だから。
相手が自分を「好きになるか」「嫌いになるか」も、相手の課題。
自分には、操作「できない」。
だから、「嫌われたら、どうしよう?」と悩む必要はない、ということです。
「自分の課題」は、相手を「信頼」すること。
もしも相手が裏切るとしたら、それは相手の課題であって、「自分のせいではない」。
何が起きても「自分のせい」ではないから、怖がることはない。
信頼の心で接すれば、相手は「味方」になります。
「味方」だからこそ、自然と貢献したくなる。
貢献とは
- 誰にやる?
- 「味方」にやる
- 何をやる?
- なんらかの働きかけ
- 何のためにやる?
- 「わたし」の価値を実感するため
- 何が実感できる?
- 自分は役に立つ人間だ
- 自分は有益な人間だ
- メリットは何?
- 自分をさらに受け入れることができる
- そんな自分をどう思う?
- こんな自分が好き
これが、「自己受容→課題の分離→他者信頼→他者貢献」の流れ。
人間不信におちいってしまった場合は、まずは「今の自分」を受け入れることからスタートです。
人を信じることは怖いのですが。
踏み出してみたほうが、人生の喜びは大きくなるし、自分を好きになることができます。
自分へのメリットが大きいと思って、少しずつでも勇気を出していきたいですね。

人間関係に疲れてしまった人は、ぜひ学んでみてくださいね。
 誰もわかってくれない寂しさを解消したい【人生は孤独】
誰もわかってくれない寂しさを解消したい【人生は孤独】
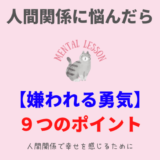 嫌われる勇気って何?【幸せな人間関係を築く】9つのポイント
嫌われる勇気って何?【幸せな人間関係を築く】9つのポイント
 自分らしく生きる3つのコツ【他人の目が気になる人が】価値を見出すために
自分らしく生きる3つのコツ【他人の目が気になる人が】価値を見出すために
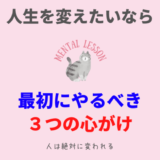 アドラー心理学【あなたは絶対に変われる】過去は関係ない
アドラー心理学【あなたは絶対に変われる】過去は関係ない