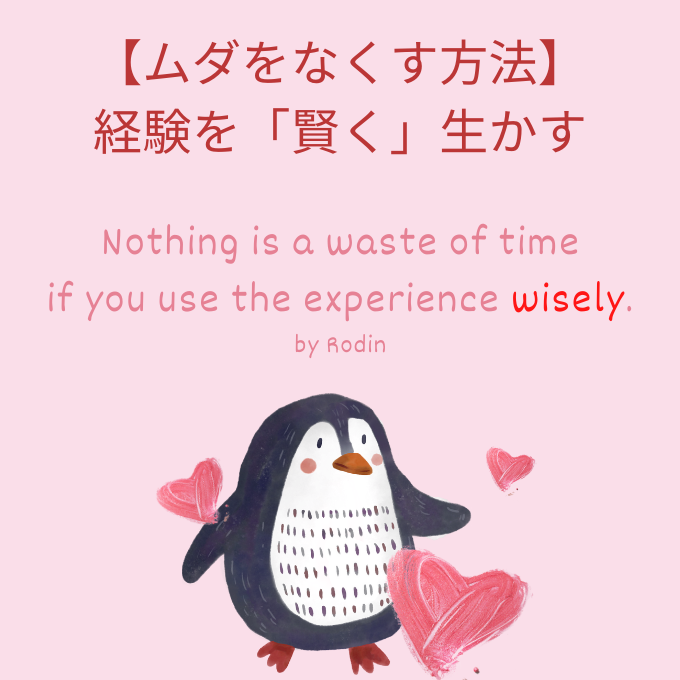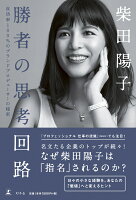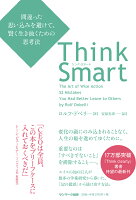皆はいろんな経験してるけど、自分には何もない
たいした経験のない人は、負けなのだろうか。
でも実は。
経験自体には意味がない

え?経験って意味ないの?
特殊な経験がなければ、今の柴田陽子はいないのでしょうか? いいえ、私は「いる」と答えます。ピンチに立たされたことがなかったとしても、つらい経験をしてこなかったとしても、やはり私は私だったと思います。
勝者の思考回路

経験は、なくてもいいのかな
- 感想
- 理由
- 想像力

無理して経験しなくていい

何か、面白い経験をしなきゃと思って焦っちゃう。
- 焦って・無理して、何かをしてみる
- 皆が行ってるから、自分も行かなきゃと思う
- 違和感・焦燥感で、疲れてしまう
何があってもなくても、自分は自分でいい
「結果的にこうなりました」というのが自然であって。
「鼻にかけるため」「経験をウリにするため」ではない。

でも、経験がないと自信ももてない。
- 感想
- 理由
- 想像力
「良い感想」は、経験を上回る
1.「感想」を持つ
「良い感想」にこだわる
「勝者の思考回路」を身につけたいなら、「良い感想」にこだわってください。
勝者の思考回路
経験が多くても、学びがない
- 遠くへ行ったけど、特に感想がない
- 新しい出合いを増やしたけど、特に感想がない
経験がなくても、学びが多い
- 目の前の些細なこと全部に、たくさんの感想を持つ
- 今の出合いから、たくさんの感想を持つ想像力

「良い感想」って何だろう?
- ナチュラルな感想でいい
- 「教えるつもり」で考えてみる
- 「あ、そういえば」を考えてみる
Point1:ナチュラルな感想でいい

「どう思う?」って聞かれたとき、恥ずかしくて答えられない。
否定することも悩むこともありません。逆に、あなただからこそ出てきた感覚だと思って、大事にしてください。
勝者の思考回路
「感想」って、本来は独自のもの。
「自分はこう思った」、それだけでいい。
今、感想が持てなければ、どこへ行っても感想は持てない
今目の前にあるものに感想を持てない人が、新しいものに出合ったからといって面白い感想を持てるわけがありません。
勝者の思考回路

どうすれば感想が持てるんだろう。
Point2:「教えるつもり」で考えてみる
- このことを他人に教えるとしたら、何をどう伝えよう?
- これは、誰の役に立つだろう?
「他人に教えよう」と思うと、「相手にとって価値になるもの」を必死で探しますよね。
そこから、自分でも思ってもみなかった感想が出てくるもの。

「今日のお昼ごはん」っていう授業を作ってみよう。
Point3:「あ、そういえば」を考えてみる
- 「あ、そういえば」○○と共通している
- 「あ、そういえば」似たようなことを誰かも言っていた
- 「あ、そういえば」このやり方で◯◯さんも成功していた
「今、目の前にあるもの」と、「まったく別の何か」との共通点を見つける。
すると、自分の考えに「つながり」と「深み」が増えるようです。

あ、そういえば、「ランチ少なめ」が午後の集中力をアップさせるって聞いたことがある。
「良い感想」には、必ず理由がある
2.「理由」を持つ
「理由」こそが、「伝える力」になる
なぜ私がこう言うのか、なぜこの行動をとっているのか、なぜこれを選んだのか……という「理由」で相手の心を動かせなければ、そこからいい方向へ物事を進めることなど、当然ながらできません。
勝者の思考回路
- 理由がないことは、ひとつもあってはいけない
- どんな些細なことにも、理由を持つ
- そもそも世の中に、理由のないものなど存在しない

そこまで理由にこだわらなきゃいけないの?
人の心を動かすものは「理由」だから
人間は「理由」を知りたがる。たとえ根拠のない理由であっても、私たちには理由が必要なのである。
人の上に立つ人間は、そのことをきちんと理解している。「理由」を告げなければ、社員のモチベーションは低下する。
シンク・スマート

根拠がなければ理由じゃないと思ってた。
「想像力」は、根拠を上回る
3.「想像力」を持つ
- 相手の欲求を認める想像力
- 「何を認められたい」と思っているだろうか
- 「知らなかった」は想像力の欠如
- 他人に「良い影響」を与える想像力
- ここで私が逃げなければ、誰に勇気を与えられるだろうか
- 逃げたくなったとき、踏みとどまる最大の力
- 「私だけが苦しい」から抜け出す想像力
- 私のために尽力してくれてる人は誰か
- 陰の支えに目を向ける
大変な状況になると、自分ばかりが苦労していると思っていないか?
自分のために何かしてくれる人は、それ以上に尽力してくれていることがよくある。大変なときこそ、自分を労わるより、相手への敬意を忘れないこと。
勝者の思考回路

「自分だけが苦しい」は、想像力の欠如?
「自分の想像力が足りなかった」と考えてみよう。
「知ろうとする」ことは、「経験を増やす」ことに上回る。
すべては、「知ろうとすること」から始まる
あなたがこれを望んでいなかったなんて知らなかった。
あの人が傷ついていたなんて知らなかった。
……たしかに知らなかったのだけれど、それは「知ろうとしなかったから」です。
知らないのも罪なら、知ろうとしないのも罪。
勝者の思考回路
どんな些細なことにも「良い感想」を持ち、「理由」を持ち、「想像力」を持つ。
それを、ひとことで言うと。
「知ろうとすること」
知ろうとしない限り、感想も理由も、持てません。
知ろうとしない限り、何も学べないのです。
まとめ
「経験のなさ」を気にするより、「感想のなさ」を気にする
小さなことでもいいのです。人からは小さく見えても、あなたにとって大変なことであれば、それは価値のあるもの。
あなたにとって大変なことから、あなたが逃げなかったという事実が大切です。その事実こそ、周囲の人を勇気づけることができるのです。
勝者の思考回路
- 「良い感想」を持つ
- ナチュラルな感想で、独自の視点を
- 他人に教える「授業」を考えてみる
- 「あ、そういえば」を増やす
- 「理由」を持つ
- どんな些細なことにも、理由を持つ
- 理由があれば説得力が増す
- 理由こそ、「知性」のカギ
- 「想像力」を持つ
- 「相手の欲求」を想像する→喜ばれる
- 「誰に勇気を与えられるか」を想像する→忍耐力がつく
- 「私のために尽力してくれてる人」を想像する→敬意を感じる
- 「知らなかった」を言い訳にしない
- 「知ろうとする」こと
- どんな小さなことからも、「何かを知る」

「今日の感想」は何だろう
参考図書
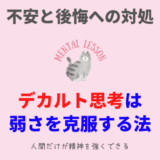 これだけで不安と後悔から抜け出せる【デカルト思考】考えるコツはたった一つ
これだけで不安と後悔から抜け出せる【デカルト思考】考えるコツはたった一つ
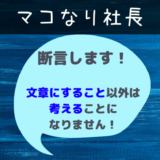 マコなり社長も認める、「ゼロ秒思考」のメモ書きの効果
マコなり社長も認める、「ゼロ秒思考」のメモ書きの効果
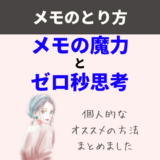 メモの魔力とゼロ秒思考【メモのとり方】オススメの方法まとめ
メモの魔力とゼロ秒思考【メモのとり方】オススメの方法まとめ
 エッセンシャル思考【優柔不断で悩む人に】おススメの1冊|主体的に生きるコツがわかる
エッセンシャル思考【優柔不断で悩む人に】おススメの1冊|主体的に生きるコツがわかる