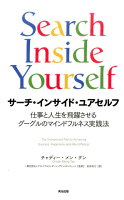ほかの人は楽しそうなのに、自分だけ人生がつまらない。
周りを見ると、なぜか落ち込む。
でも、それは単なる比較の問題かもしれない。
幸福な生活にとって必要なことは退屈に堪(た)えるというある程度の力である。
ラッセルの幸福論

堪えなきゃいけないの?
なにかまじめな建設的な目的をもっている少年や青年は、その目的を達成するために途中で必要だということを悟るならば、進んで相当の退屈にもみずから堪えるだろう。
ラッセルの幸福論

建設的な目的って、なんだろう。
(遊び中心の人は)自己陶酔状態に陥っており、今すぐここで楽しくなるかどうかで人生のすべてを解釈し評価してしまうのである。
7つの習慣
「毎日がつまらない」のは、アタリマエのこと。
わざわざ、楽しいことを追い求める必要はないかもしれません。
いかなる偉大な生涯もすべて大しておもしろくもない部分を含むものであった。
ラッセルの幸福論
毎日がつまらないのは、なぜ?
- 刺激が足りない
- マンネリにおちいってる
- 非日常感を味わってない
- 旅行や趣味などを楽しめてない

たくさん旅行をしている人は、刺激が多そうでうらやましい。
あまりに多く旅行する、あまりにさまざまな印象を持つ、これは若い人々にとってはいいことではない。
ラッセルの幸福論

え? なんで?
興奮によって満たされた生活は、疲労困憊の生活である。そこではスリルを与えるために、絶えずいっそう強い刺激が必要になり、スリルは快楽の一つの本質的な部分として考えられるようになってしまう。
ラッセルの幸福論

たしかに、家に着いたらグッタリしてる。
刺激や興奮を求めると、逆に疲労困憊。
だからこそ、多くの旅行や経験は必要ないというのです。

結局、どうしたらいいんだろう。
退屈を回避しようとすると、空虚感が生まれる
比較が、退屈を生む
- 今の生活とは別の、快適な生活があることを知ってしまった
- 快適な生活と比較することで、退屈への不満が生まれる
- 退屈への不満を、「興奮」状態によって解消しようとする
- 興奮からは、空虚感しか生まれない

他人の生活を知ってしまったときに、焦って何かをしてしまう
退屈に堪えられない人は、「興奮」を求める
(退屈は)興奮を充分勢いよく追求することによって避けられるものだということを知るようになったし、あるいはそう思い込むようになっている。
ラッセルの幸福論
退屈への不満を、一時的に解消しようとする。
それが「興奮」の追求。
戦争や虐殺さえも、退屈からの逃避、興奮の追求であると、ラッセルは言いいます。

興奮を求めると、悪い事をしたくなるのかな。
興奮は、空虚感を生むから
あまりに多くの興奮に馴(な)れてしまった人は、たとえばおそろしく胡椒(こしょう)の好きな人に似ている。彼は他の人だったら息の詰まりそうになるほどの胡椒の分量でなければ、最後にはこれを味わうことができなくなる。
ラッセルの幸福論

楽しいことをしたあと、虚しくなって、またすぐに求めたくなる。
もっともっとと求めた結果、良くないことに手を付けることもあるかもしれません。
次の興奮を得るためにお金を稼ぐなら、何のためにお金を稼いでいるのか、わからなくなります。
興奮を提供してくれる連中は、永久に一つの場所から他の場所へ、彼らの行くところに、陽気とおどりと飲酒をふりまきながら動きまわっている。ただし、どういうわけか、彼らはいつもこうした楽しみを新しい場所でたのしもうと期待しているのだが。
ラッセルの幸福論
退屈から完全に解放されるのは、難しい
働く必要から解放されるに足るだけの金を持っている連中は、退屈から完全に解放された人生を、彼らの理想として描いている。
(中略)
この理想もまた、他のいろいろな理想と同じように、理想家たちが想像するほど実現が容易でないことを、私は恐れるものだ。とにかく前の晩が楽しかったその割合で、あくる朝は退屈なものである。
ラッセルの幸福論

夜が楽しいと、翌朝は退屈になる。どうしたらいいんだろう。
本当の幸福は、静かな生活の中にある
幸福な生活とは、だいたいにおいて静かな生活でなければならない。なぜなら、静けさという雰囲気のなかでのみ、真の歓喜は生きることができるからだ。
ラッセルの幸福論
「静けさ」とは、「単調」「マンネリ」。
- 単調
- マンネリ
- 退屈
実は、そんな静かな日々の中でこそ、偉大なものが生まれるのだといいます。

え? 単調はよくないと思ってた。
幸福には、「退屈に堪える力」が必要
幸福な生活にとって必要なことは退屈に堪えるというある程度の力である。そしてこういう能力こそ青年たちに教えられねばならぬものの一つである。
ラッセルの幸福論
すべて偉大な書物というものは、退屈な部分を持っている。そしていかなる偉大な生涯もすべて大しておもしろくもない部分を含むものであった。
退屈に堪える力
偉大な書物も、偉大な人物の生涯も、その大部分は退屈。
なぜなら、偉大な書物も、偉大な人物の生涯も、その大部分は、退屈な部分で占められているから。
退屈な部分がなければ、偉大なものは得られないのかもしれません。
気晴らしや道楽などの興奮は、長期的な視野をさまたげる
遊び中心の人はすぐ今味わっている楽しさのレベルに飽きてしまい、常に「もっと欲しい! もっと欲しい!」と叫び出す。だから次の楽しみがもっと大きく、もっと強烈で、もっとエキサイティングで、もっと興奮させてくれるものでなければ、満足できなくなる。こうした人たちは完全に自己陶酔状態に陥っており、今すぐここで楽しくなるかどうかで人生のすべてを解釈し評価してしまうのである。
7つの習慣

目の前の快楽に、心を奪われてしまう。
つまり。
今が、楽しいかどうか。
それが解釈の基準になると、長期的な展望が持ちづらくなります。
建設的な目的があれば、退屈にもみずから堪える
なにかまじめな建設的な目的をもっている少年や青年は、その目的を達成するために途中で必要だということを悟るならば、進んで相当の退屈にもみずから堪えるだろう。
ラッセルの幸福論
「目的」をもつことによって、退屈に堪える力をつけることができる。
夢や目標は、退屈に対抗するために持つのかもしれません。

夢がないから困ってる。
不安を取り除く努力よりも、意義の達成に喜びを感じよう
人間が本当に必要としているのは不安のない状態ではなく、価値ある目標のために努力することである。人間に必要なのは何としてでも不安を取り除くことではなく、意義の達成に使命を感じることである。
ヴィクトール・フランクル(精神科医)

不安を感じたくないから、楽しいことに逃げるのかもしれない。
目先の興奮に流される人は、結果的に、つまらない人生を送ってしまうことになるといいます。
偉人の人生は、エキサイティングとは無縁
多くの偉人の生涯もまた、若干の偉大な瞬間をのぞけば、エキサイティングなものではなかった。
(中略)
静かな生活が偉大な人々の特質であったということ、そしてまた、彼らの快楽が外ばかり見たがるような眼の持ち主には刺激的と映ずるごとき種類のものではなかったということ、こうしたことがわかるだろう。
ラッセルの幸福論
- 静かな生活を送っていた
- エキサイティングな人生ではない
- 偉人にとっての快楽は、凡人にとっては刺激的ではない
ソクラテスの場合
彼の一生の過半は妻クサンチッペと静かに送られたものであり、午後には運動をするとか、道ばたで若干の友人に出会ったとかいうことであったろう。
ソクラテス
カントの場合
カントは彼の一生を通じて、一度もケーニヒスベルクの町から十マイル以上出たことはなかったと伝えられている。
カント
ダーウィンの場合
ダーウィンは、世界周航をしてからは、彼の生涯の残りの全部をその自宅で過ごしている。
ダーウィン
マルクスの場合
マルクスは、二、三の革命運動を煽動してからは、大英博物館で彼の残された年月を過ごそうと決意している。
マルクス
- つまらないものと比較しない
- 他人の生活に嫉妬しない
- 刺激的なものに興味がない
- けっこう地味に暮らしている
- 本当に大事な、人生の目的をもっている
私たちはもっと、静かな生活を求めてもいいのかもしれません。
派手さ・刺激・興奮は、常に他者との比較なので、疲れてしまいます。

本当は静かなほうが落ち着く。